天下一品の大量閉店に学ぶ 東京で個人事業主が倒れないための“経営構造”の作り方
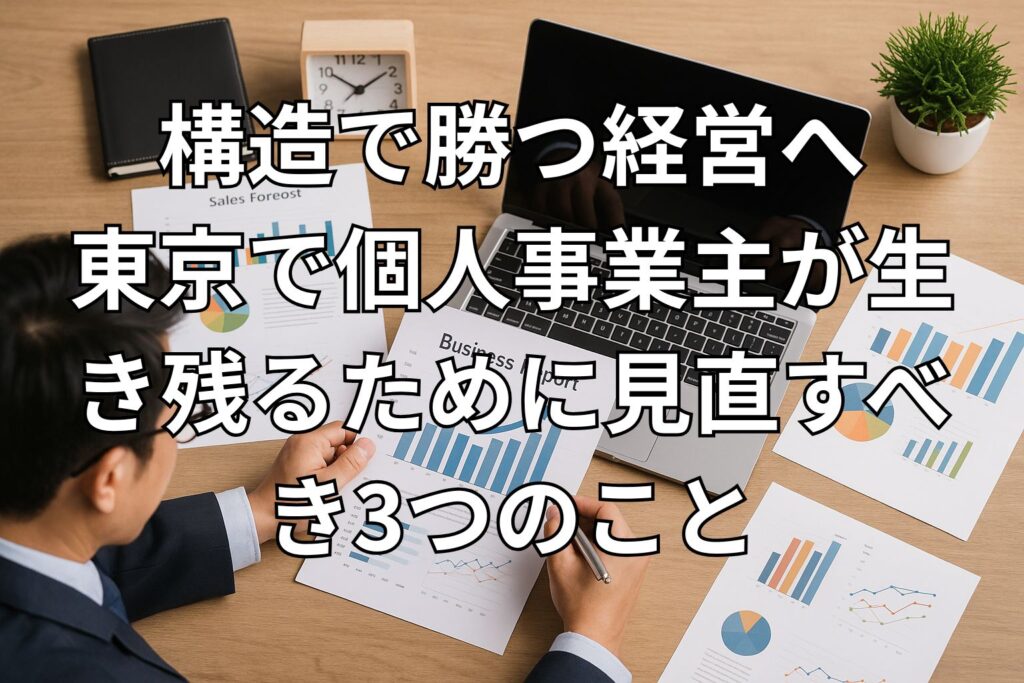
- 2025.06.30配送コラム
-
天下一品の大量閉店に学ぶ 東京で個人事業主が倒れないための“経営構造”の作り方
構造で勝つ経営へ──東京で個人事業主が生き残るために見直すべき3つのこと
2025年6月、人気ラーメンチェーン「天下一品」が東京都内で10店舗以上を一斉に閉店したニュースが話題を呼びました。
「味に問題はなかった」「ファンもいた」「価格も妥当だった」──それでも、店は閉まりました。この出来事は、軽貨物をはじめとした個人事業主や経営者にとっても、決して他人事ではありません。
一見順調に見える事業でも、“構造が崩れた瞬間に一気に倒れる”という現実がそこにはあったのです。売上があるのに崩れる“構造リスク”とは?
天下一品の閉店理由は、ブランドや商品そのものではありませんでした。
問題は、運営会社の経営構造にありました。多店舗展開に伴う管理コストの増大、標準化されないオペレーション、利益が出にくいロイヤリティ体系、時代に合わない業務設計…。
こうした“見えない構造の綻び”が、静かに経営体力を削っていったのです。これは、飲食業に限らず、東京で軽貨物配送を行う個人事業主や中小企業経営者にも当てはまります。
生き残る経営者が実践している3つの構造戦略
1.売上より「利益の再現性」を設計する
目先の売上に一喜一憂するのではなく、利益が継続して生まれる構造を持っているかが問われます。
たとえば、契約の仕組み化や、業務の属人化を排除する仕組みづくり。
さらに、顧客との関係性を深めて「単発」ではなく「継続」に切り替える設計が求められます。2.拡大より「連携」で支え合う
全てを自社完結で抱えようとすると、成長の限界も早く訪れます。
だからこそ、他社・他人との“連携”が重要になります。
業務の一部を提携企業とシェアしたり、協業により人材や案件を流動化させることで、持続性のある経営が可能になります。3.複層型の「ミルフィーユ経営」でリスク分散
単一収益モデルでは、社会や市場の変化に弱くなります。
主力事業に加え、周辺ニーズを収益化できる「重ね構造=ミルフィーユ型」の事業設計を行うことで、収益源を分散し、安定性を高めることができます。構造で事業を守る──すべての経営者に必要な視点
経営者や個人事業主にとって本当に大切なのは、
「良いサービスを作ること」ではなく、「それを持続可能に届ける仕組みをつくること」です。天下一品の閉店から私たちが学べるのは、
「商品がよくても、組織がよくても、構造が壊れれば事業は潰れる」という厳しい真実です。東京で軽貨物配送を営む個人事業主の方はもちろん、
小売・飲食・士業など、あらゆる業種の方にとって、今この“構造の棚卸し”が求められています。軽貨物新規事業支援のご案内
ハウンドジャパンでは、東京・神奈川を中心に軽貨物事業を支える
「新規事業支援」「起業支援」「構造設計支援」などを行っています。軽貨物新規事業に興味のある方は、以下のページで詳細をご覧ください。
軽貨物新規事業支援に興味のある方はこちら「売上があるのに続かない」と感じたら、それは「構造にひずみがあるサイン」かもしれません。
今こそ、土台から見直すタイミングです。構造で勝つ。
それが、未来に残る経営の第一歩です。
