変化の波に乗れ──軽貨物配送が“社会的意義ある仕事”であり続けるために
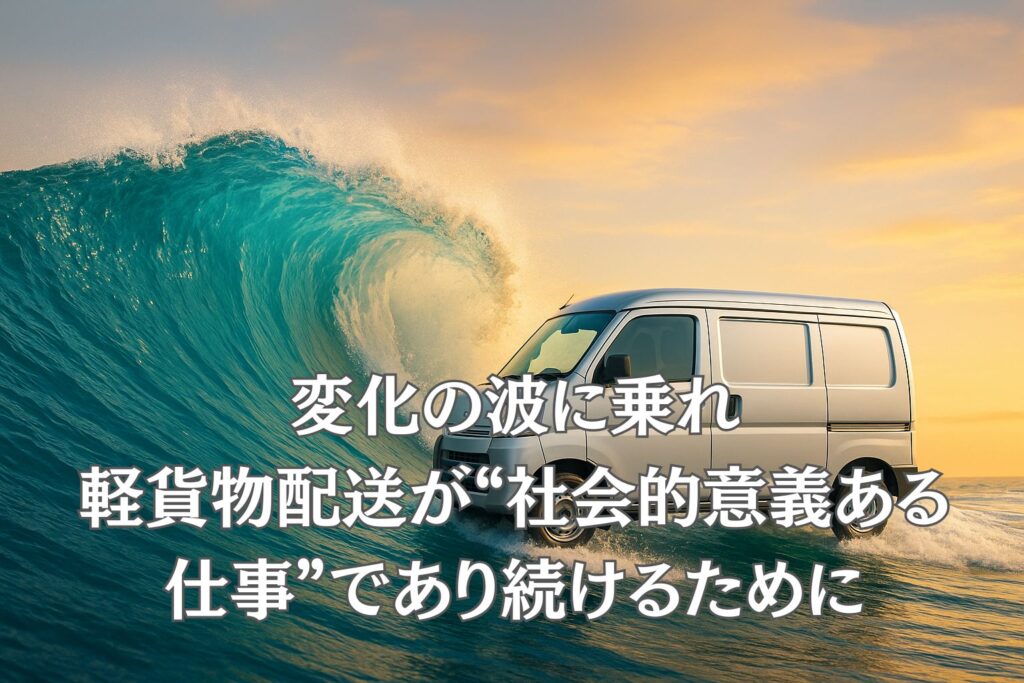
- 2025.07.08配送コラム
-
変化の波に乗れ──軽貨物配送が“社会的意義ある仕事”であり続けるために
東京・横浜で軽貨物起業を考える方へ──進化する自動運転時代を迎えて配送業がとるべき道
2025年、テスラがロボタクシーを米オースティンで本格運用開始したというニュースが大きな話題を呼びました。
救急車に自動で道を譲る様子がSNSで拡散され、ついにAIが人間に近い判断を下せる時代が始まったことを実感した方も多いのではないでしょうか。しかしこの進化は、私たち軽貨物配送業界にとって決して他人事ではありません。
自動運転技術の進化は、配送の自動化、そして“人手不要”という未来へとつながっていくからです。
特に、東京や横浜といった都市部ではその影響が顕著になると予測されます。本コラムでは、自動運転車が抱える課題と進化、そして軽貨物配送業界が今すべき生き残るための具体的戦略について、
起業を検討している方々に向けて実践的な視点から深掘りしていきます。自動運転の進化は「現実」へと移行中
テスラ、Waymo、Cruiseなど世界の大手企業がしのぎを削る自動運転の実用化競争。
今やそれは「いつ来るか」ではなく「どう対応するか」が問われるフェーズに突入しています。中でも注目すべきは緊急車両対応。
サイレン音や赤色灯を検知し、自動で徐行・停止・進路変更するという高度な判断力が実装され始めています。
とはいえ、交差点や狭路、交通混雑時などの柔軟な対応にはまだ課題があり、完全自動運転には技術的・法制度的な壁が存在します。日本ではV2I(車とインフラの通信)などの規格化が進められており、
自動運転の普及は一気には進まず段階的に進化していくと見られています。それでも「人」は確実に減る
都市部や幹線ルートなどルーティン性の高い配送は真っ先に自動化が進みます。
つまり「すべてのドライバーが必要」という時代は、確実に終わりを迎えるということです。この流れは、大手プラットフォーム主導で急速に進む可能性があり、
軽貨物業界の中小事業者やこれから起業を目指す方にとっては脅威であると同時に、大きなチャンスでもあります。生き残るための3つの実践戦略
1.人間力×プロフェッショナリズムの強化
医療系・精密機器・企業間の重要便など「信用」が求められる配送は、AIには代替できません。
単なる労働力ではなく、“信頼される配送員”としての価値を高めるべきです。2.ITスキルの標準装備化
配送アプリや遠隔サポート、ナビAIとの連携など、ITとの共存が前提となります。
ドライバーにも業務遂行力を高めるためのIT教育が求められます。3.ビジネスモデルの再構築
自社案件の一部に自動化技術を導入し、人材は高単価・非定型案件に集中。
さらに契約支援や業務委託管理など、軽貨物の周辺事業にも収益源を広げる視点が重要です。ハウンドジャパンのビジョン──共存と誠実
軽貨物事業者が生き残るためには、「配送=人がするもの」という固定概念から脱却し、
「人は価値の高い配送に集中」「ルーティンはAI・ロボへ」という戦略的な切り分けが不可欠です。私たちハウンドジャパンは「誠実」であることを理念とし、
AIやロボットと競争するのではなく共存する道を選びます。軽貨物配送という仕事が社会に必要とされる存在であることを、
携わる人が胸を張って語れる業界をともに築いていきましょう。軽貨物起業・新規事業支援のご案内
ハウンドジャパンでは、東京・神奈川を中心に
「軽貨物起業支援」「配送構造設計支援」などを行っています。軽貨物での起業や新規事業をご検討の方は、以下のページをご覧ください。
軽貨物新規事業支援はこちら自動運転時代を迎えても、
人が運ぶ意味・価値がなくなることはありません。構造を見直し、軽貨物配送という仕事に未来を宿す。
それが、次代に選ばれる経営の第一歩です。
